「この記事はPRを含みます」
ため池や田んぼ、水たまりなど身近な水辺には、大小さまざまなゲンゴロウのなかまがくらしています。
それらを捕まえて飼育したくなることも多いのではないでしょうか。
しかし、詳しい飼育方法が書籍やインターネットで紹介されている種類はごく一部で、普通種であっても飼い方や繁殖のさせ方など、情報がほとんど知られていません。
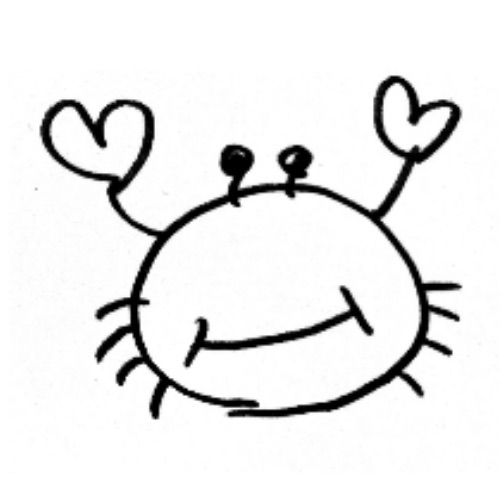
私はゲンゴロウのなかまの飼育方法に興味があります。
生きものを飼育する目的は人それぞれいろいろあると思います。
私が飼育する目的のひとつに、野外では観察が難しいその生きものの知られざる生態を、飼育下で知ることができるところにあります。
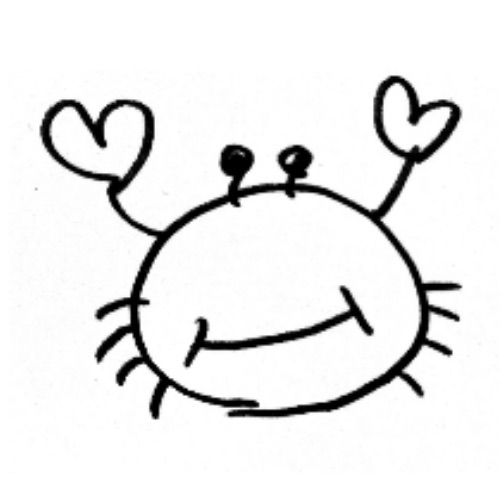
生きもののすごい瞬間を観察できたときは感動します。
また、種類によっては、野外で数を減らしているものも少なくなく、飼育方法や繁殖方法の確立は、保全の分野でも役に立つことがあります。
生きものを上手に飼育・繁殖させるには、まずはその生きものがどんなエサを食べるのかを知ることがとても重要です。
今回は、私が実際に飼育・繁殖に取り組んだ際に使用した幼虫のエサを種類別に紹介します。
本記事で紹介するエサが、ゲンゴロウ類幼虫の飼育方法の正解というわけではありません。
あくまで参考程度に見ていただき、みなさんがゲンゴロウ類の飼育により良いエサを探すきっかけのひとつになればと思いまとめてみました。
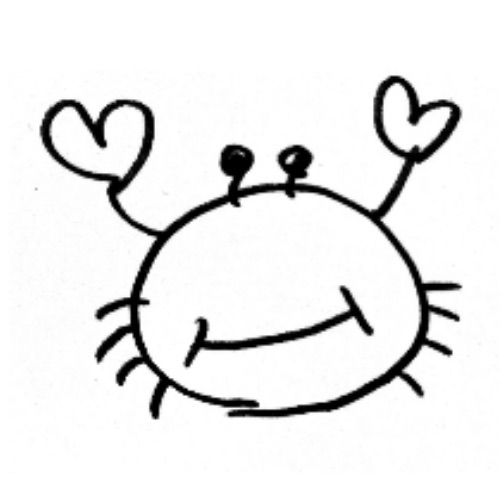
これまでに20種類以上のゲンゴロウを繁殖させて育ててきました!
ゲンゴロウ類幼虫にどんなエサを使ったのか紹介します。
ゲンゴロウを体長別に3つにグループ分け
今回の記事では、簡易的に成虫のサイズごとに3つに分けて紹介します。
クロゲンゴロウやゲンゴロウなど体長が2センチ以上のもを大型ゲンゴロウ、コシマゲンゴロウやシマゲンゴロウ など体長が1〜2センチ程度のもを中型ゲンゴロウ、そしてケシゲンゴロウやチビゲンゴロウなど体長が1センチ未満のものを小型ゲンゴロウと分けました。
この分け方は何かを参考したわけではなく、『水たまり』が勝手に分けたものです。
大型ゲンゴロウの幼虫とエサの種類
大型ゲンゴロウの幼虫には、市販の冷凍赤虫と冷凍コオロギを与えました。
孵化幼虫には冷凍赤虫を与え、幼虫の成長に合わせて、冷凍コオロギにエサを切り替えました。
ゲンゴロウの幼虫には、メダカなどの小魚を与えて育成したこともありますが、冷凍コオロギと比べて摂餌後のお腹の膨らみ具合が弱く、あまり適していないようでした。

中型ゲンゴロウの幼虫とエサの種類
中型ゲンゴロウの幼虫には、市販の冷凍赤虫をおもに与えました。
シマゲンゴロウの幼虫は、野外ではオタマジャクシを捕食することが観察されており、実際にエサとして与えるとよく食べ、成長も良い気がします。
ただし、エサとして野外からオタマジャクシを大量に採集するのは避けたいところです。水温を高めにして、多めに赤虫を入れることで、オタマジャクシを使用しなくてもシマゲンゴロウは繁殖させることができました。
また、マルガタゲンゴロウの幼虫はよく泳ぎまわり、ミジンコなどを捕食するちょっと変わりものです。
飼育下ではミジンコのほかに、冷凍赤虫を水面に浮かべて与える方法で摂餌を確認でき、幼虫を羽化までさせることができました。しかし、羽化成虫は親個体と比較すると小型のものばかりで、ミジンコや赤虫だけでは栄養が足らないものと考えられました。
マルガタゲンゴロウの幼虫を飼育下で大きな成虫にするには、エサの種類や量を工夫する必要があります。

小型ゲンゴロウの幼虫とエサの種類
小型ゲンゴロウの幼虫には、アルテミアの孵化幼生やミジンコ、市販の冷凍赤虫をおもに与えました。
孵化幼虫はどの種も小さいため、最初から赤虫を食べるの難しいようでした。
そこで試しに与えてみたアルテミアの孵化幼生でしたが、どの幼虫も捕食でき、生存率も高くなりました。
野外でも小型のプランクトンなどを捕食していると考えられます。
あとは成長に応じて、ミジンコや冷凍赤虫を与えて育成しました。
また、幼虫の頭部に特徴があるケシゲンゴロウのなかまやチビゲンゴロウのなかまは、カイミジンコを捕食しました。
カイミジンコはエサとして与えなくてもちゃんと成長しますが、捕食シーンが面白いので機会があればぜひ試してほしいエサのひとつです。

ゲンゴロウ類幼虫の飼育と今後
ゲンゴロウのなかまには、成虫・幼虫問わず、野外で何を食べているのか分かっていない種類が多くいます。
飼育下では、安定して入手可能な市販の冷凍赤虫を与えることがどうしても多くなりがちです。
しかし、野外ではまだ誰にも知られていない特異的なものをエサとして捕食している可能性もあります。
幼虫の育成には、飼育下での情報だけではなく、野外での観察事例も重要な情報になります。
今後もエサについては飼育下、野外問わず知見を増やし、生存率や成長効率の良いエサを探っていく必要があると考えています。
また、野外で詳細な繁殖時期が分かっていないゲンゴロウもいます。
飼育下と野外ではさまざまな条件が異なりますが、野外での繁殖期を解明するヒントが飼育で得られた情報の中にあるかもしれません。みなさんが飼育して得た情報がいつか新しい発見につながるかもしれませんよ。
今回、紹介したゲンゴロウ類多くは、体長が数ミリしかないものだったり、興味のある人しか知らないような種類ばかりです。今後も飼育したことない種類のゲンゴロウ類の繁殖に取り組み、情報を発信していきたいと思います。
本記事が私と同じように飼育観察される方の少しでも参考になればうれしいです。



